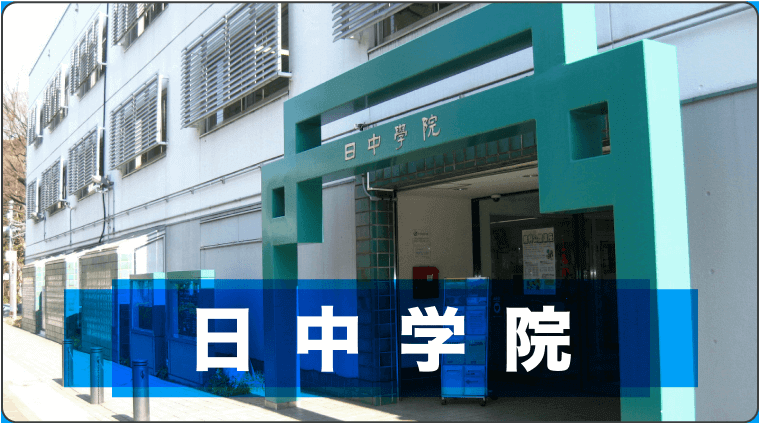「JENESYS2024」 2024年日中障害者福祉青年交流代表団 フォローアップ オンライン交流
本プログラムは、2024年8月に訪日した中国障害者連合会及び関連機関の関係者が、日本側受け入れ先の関係者とオンラインで交流し、帰国後も日本の同分野への理解を深めるほか、日中関係者の友好関係を促進することを目的として実施しました。


Contents
Highlight
代表団団員による発表では、訪日時の振り返りのほか、中国における障害児童教育の取り組み、障害生徒の職業訓練についてなど、中国の状況を紹介しました。また、日本側からは、事前に中国側から提供された質問・関心事項について回答したほか、在校生徒がデジタルリハビリに参加している様子などを紹介しました。
中国側参加者からは「選挙権が与えられた満18歳の生徒に対する、選挙に関する教育は、何科の先生が担当しているか」「心理的な教育においてどのような取り組みを行っているか」など、多くの質問や意見が挙がりました。
実施概要
| 実施日時 | 2025年2月20日(木) 15:00~17:10(日本時間) |
| 参 加 者 | 中国側:29名 「JENESYS2024」2024年日中障害者福祉青年交流代表団 団員 |
| 日本側: 2名 東京都立水元小合学園関係者 | |
| 実施団体 | (公財)日中友好会館 |
| 協 力 | 中国障害者連合会 |
| 内 容 | 団員による訪日の振り返り、質疑応答・意見交換、代表団団長による総括 |
| 実施方法 | Web会議サービス「Zoom」を使用したオンライン交流 |
主なプログラム
① 趣旨説明、参加者紹介
② 中国側:当時の団員2名による訪日の振り返り発表
③ 日本側:当時の訪問先関係者より中国側からの関心・質問事項について回答
④ 質疑応答・意見交換
⑤ 代表団団長による総括
参加者の感想
◆訪日時に見たこと感じたことが、この交流で再び示され、昇華されました。今回の交流活動は中日双方の交流だけでなく、中国の遠く離れた団員同士の交流でもありました。私たちが関心を持っている問題は似ていることが分かり、共感することも多くありました。
どの国でも障害者が似たような苦境や社会的地位の相対的な劣位に直面しています。障害者に関わる業務をしている人の中には、私と同じ障害者もいて、皆が障害を克服し、平等に発展する方法や道を模索しています。これらの経験や方法について情報交換をすることは、自分自身を充電させるとても素晴らしいシステムだと思います。
◆今回の交流で、東京都立水元小合学園の校長より、障害を持つ生徒に対する市民権教育について紹介を受けました。日本では18歳で成人となり選挙権を持ちます。障害のある生徒にも選挙に関する教育を行うとのことで、これはとても印象的でした。選挙について担任や社会科の教師が生徒に教え、実際の選挙では投票用紙に記入する時などにサポートを受けられることを知りました。
また、昨年、水元小合学園を訪れた時、校内で就任したばかりの生徒会長のポスターを見て、生徒の全体的な潜在能力を育成する学校の取り組みに感動しました。双方が今後、障害のある生徒への教育についてより深く交流できることを願っています。
◆日本側からの詳細な説明を受け、日本の障害者特別支援教育について、より深く理解することができました。特に特別支援学校が企業と連携して、企業のニーズや市場のニーズに基づいた職業教育プログラムを開発し、高校で特別職業教育を受けた学生が100%就職できることに、非常に感銘を受けました。企業に就職できない重度障害者の学生に対しては、充実したフォローアップ体制があり、彼らは卒業後に社会福祉施設に入所し、可能な範囲で雇用を支援しています。同時に、学校では最新の科学技術手段を障害児童の教育に活用し、彼らの学習とリハビリの質を向上させており、これらはとても参考になると思いました。