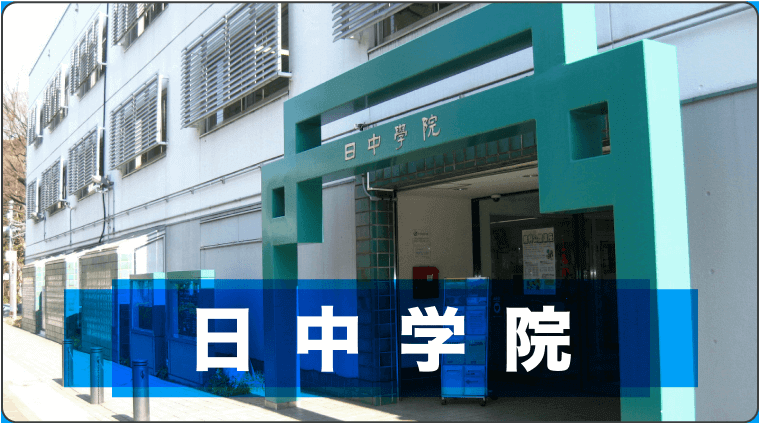「六分の侠気 四分の熱」 ―中国演劇界の劇作家たち

菱沼 彬晁
公益財団法人国際演劇協会日本センター 理事 日本語の「新劇」は死語になってしまいましたが、これに相当する中国語は「話劇」でしょうか。日中演劇交流の活発化を望む新劇人に後押しされて日本に「話劇人社」が発足したのは1979年、理事長は演出家の日笠世志久さんから俳優の伊藤巴子さんに引き継がれました。支援者に演劇評論家の尾崎宏次さん、俳優の杉村春子さんらの名が見えました。私が話劇人社の活動を知ったのは1986年、当時43歳の私は日本文化財団に在籍しており、江蘇省昆劇院の『牡丹亭』訪日公演の実務と『牡丹亭』台本の翻訳を担当し、話劇人社の皆さまにPRと集客のお願いをしていました。1987年、ひょんなことで話劇人社の事務局長をお受けすることになってから、私の第二の人生の悪戦苦闘が始まりました。
先代市川猿之助さん(現、猿翁さん)から松竹を通して中国の劇作家に書き下ろしを依頼したいという打診がありました。俳優で舞踊家、猿之助さんの奥さまでいらっしゃる藤間紫さんのために西太后の一代記を舞台化し、ご自身は演出を担当するとのこと。私はすぐ「分かりました」と答えました。というのは、1994年に中国戯劇協会訪日団のメンバーの一員として清朝夏の離宮・避暑山荘のあった承徳市から劇作家で承徳話劇団の団長の孫徳民さんを迎え、彼が若き日の西太后をモデルに『懿貴妃(いきひ)』を書いていたことを知っていたからです。しかし、今度は西太后という複雑怪奇な人物の一代記で締切は半年後。無理を承知の原稿依頼でした。私は厳寒の承徳へ向かいました。孫徳民さんは羊のしゃぶしゃぶでもてなしてくれ、日本人は冷やしたビールしか飲まないからと、大きな薬罐にビールをどぼどぼと注いで氷点下の戸外に置き、ビールの氷ができるまできんきんに冷やしてくれたのを今も忘れません。孫徳民さんは迷いに迷い、根負けの形で執筆を引き受けてくれました。壮大な構想と緻密な構成による西太后一代記は1995年、新橋演舞場を皮切りに大阪、福岡、名古屋、再び新橋演舞場での凱旋公演へと続き、藤間紫さんは「圧倒的な存在感を見せつけた」と評されました。
1997年、中国戯劇家協会の訪日団を迎えて日中演劇人のシンポジウムを開いたとき、メンバーの一人に湖北省武漢市に住む劇作家の沈虹光(しん・こうこう)さんがいらっしゃいました。討論の資料として彼女の最新作『長江乗合船(原題・同船過渡)』が事前に送られてきました。1994年に曹禺戯劇文学賞を受賞した作品でした。しかし、翻訳を人に依頼する予算も時間もなく、やむなく自分で翻訳して配布しました。以来、私は中国の劇作の翻訳を数多く手がけることになりましたが、いつもこうした必要に迫られたからでした。この作品が劇団東演の目に止まり、1998年の初演以来、日本縦断公演を何度も繰り返す大ヒットになりました。
シンポジウムの席が緊張する場面がありました。参加者から「中国の劇作家は国家から“主旋律” の縛りで自由にものを言えないのではないか」という質問です。沈さんは「私は普通の人々の生活を重視し、この中に社会や国の運命を反映させることができると考えています。普通の人々の懸命な生き方がなければ、社会と国に何の真実と善美があるでしょうか。これが私の主旋律です」と答え、期せずして会場から大きな拍手が沸き起こりました。私は今もこの会場の光景を感動をもって思い出します。
私は中国の演劇界に多くの友人を得ることができました。その一人が「中国人には今も孔子の血が流れている」と語り、私はなるほどと納得しました。日本人の私の中には同じように与謝野鉄幹の詩「友を選ばば書を読みて 六分の侠気 四分の熱」の一句が生きています。どこの国であろうと、また時代や政治がどう変わろうと、私は友人に対して「六分の侠気 四分の熱」を守って生きたいと考えています。