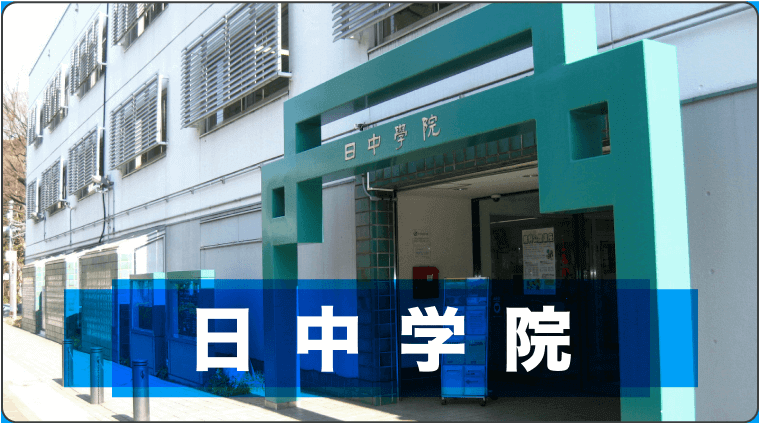「JENESYS2024」第二十六回中国教育関係者代表団
本事業は、1996年度より継続する、中国の小・中・高等学校の教員並びに教育関係者の招聘事業で、26回目となる今回は、「小・中・高校生へのネットリテラシー教育」をテーマに、各種教育機関への訪問・視察等を通じて日本の教育について理解し、日本の教育関係者と交流を図るほか、日本に対する包括的な理解を促進することを目的として実施されました。



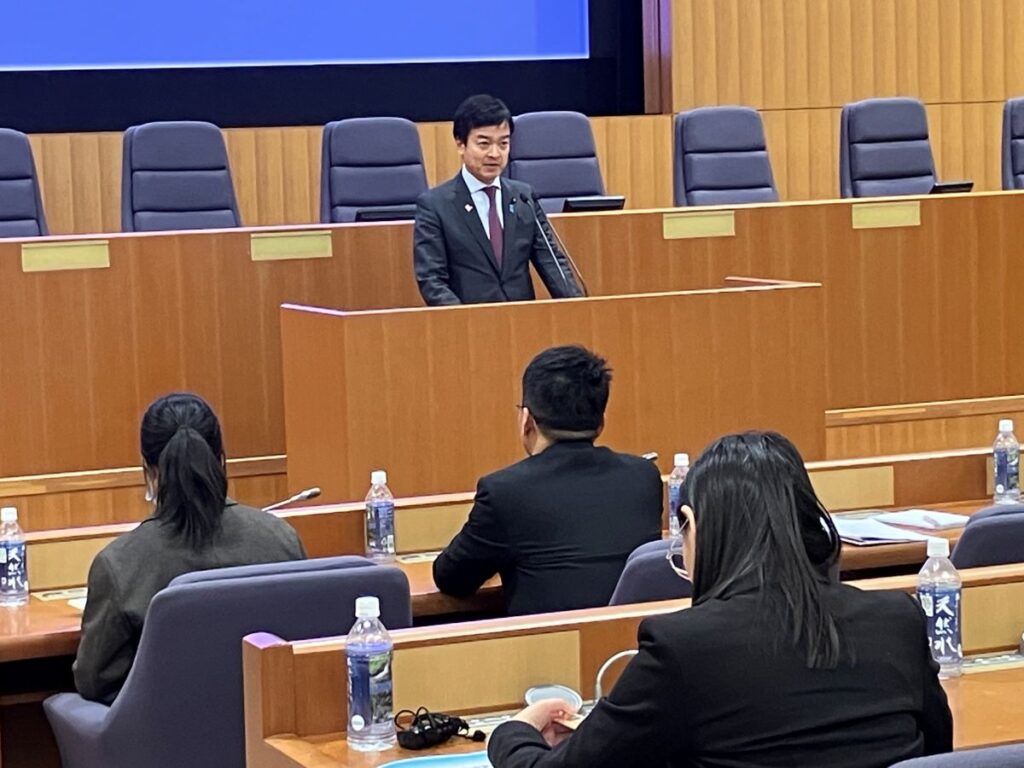


Contents
Highlight
小中学校や埼玉県教育局を訪問
小中一貫校の品川区立品川学園では教職員との交流に加えて、中国語が堪能な生徒の案内で校内見学したほか、給食体験も行いました。また生徒会とも懇談し、児童・生徒とも十分に交流できました。
千葉大学教育学部附属中学校では、前年10月に実施した日本青年教育関係者訪中団に参加した教員が、訪中時の報告を含めて、ネットリテラシー教育の取り組みを説明したほか、教職員と意見交換を行って活発に議論しました。
団員は教職員と生徒が温かく歓迎してくれたことや、生徒たちが楽しそうに学校生活を送っている姿に感銘を受けていました。
また、埼玉県教育局では、テーマに関するブリーフと懇談会を実施し、県下のネットリテラシー教育の現状について詳細な説明を受け、教育局の役割と教育現場での対応について理解を深めることができました。
環境学習施設や防災施設を参観
環境学習施設「エコルとごし」と、防災体験施設のさいたま市防災センターを訪問し、学校外の施設を有効利用した、日本の実践的な教育についても理解を深めました。
実施概要
| 招聘期間 | 2025年1月20日(月)~1月24日(金) 4泊5日 |
| 招聘人数 | 30名(団長、事務局2名、団員27名) |
| 実施団体 | (公財)日中友好会館 |
| 派遣団体 | 中国日本友好協会 |
| 訪日テーマ | 小・中・高校生へのネットリテラシー教育 |
| 内 容 | ・日本の教育に関するブリーフ、教育関係者との懇談 |
| ・小学校・中学校の訪問、授業参観、教職員との交流 | |
| ・日本に対する包括的理解促進につながるプログラム等 |
主な日程
| 1月20日(月) | PM | 羽田空港着 |
| 都内参観、歓迎会 | ||
| 1月21日(火) | AM | エコルとごし(環境学習施設)参観 |
| AM-PM | 品川区立品川学園訪問・交流 | |
| PM | 文部科学省ブリーフ、外務省表敬訪問 | |
| 1月22日(水) | AM | 埼玉県教育局との懇談会 |
| PM | さいたま市防災展示ホール参観 | |
| 1月23日(木) | AM | 千葉大学教育学部附属中学校訪問・交流 |
| 千葉大学キャンパスツアー、歓送報告会 | ||
| 1月24日(金) | AM | 都内散策 |
| PM | 帰国 |
参加者の感想
◆日本の外務省と埼玉県教育局を訪問した際、両国の小中学生に対するインターネットリテラシー教育について、日本の政府部門関係者と深い意見交換を行いました。交流を通じて、小中学生に向けたオンライン教育分野における日本のマクロ計画と開発の方向性をより包括的に理解することができ、また、日本政府が小中学生向けのオンライン教育を非常に重視していることを感じました。また日本の学校も訪問し、その過程で日本の教育の細部や個性へのこだわりを深く感じました。校内環境のレイアウトからカリキュラムの慎重な配置まで、すべてが学生の総合的な成長への重視を体現していました。このような学生の主体的地位の尊重は、中国で提唱されている質の高い教育の理念と一致しています。両国の教育は、文化的背景や教育制度に違いはありますが、学生の総合的な成長を追求するという目標は非常に一致しています。また、カリキュラム設計や授業評価等についても、学校の先生や学生と深く意見交換しました。互いの経験や悩みを共有したことが、今後の教育実践のための新たなアイデアにつながったことは間違いありません。教育分野での交流に加え、品川区の環境保護施設やさいたま市防災展示ホールも見学しました。品川区の環境施設を視察した際には、日本のゴミ分別や資源リサイクルに関する高度な技術と成熟した経験を目の当たりにしました。これらの貴重な経験は、環境保護の発展を促進し、中国に美しい故郷を築くために大変参考になります。さいたま市防災展示ホールでは、地震や火災などの災害シナリオを模擬体験することで、日本の防災減災教育の体系的な性質を学びました。誰もが基本的な防災知識と緊急時対応能力を身に付けられるようにしていて、非常に学ぶ価値がありました。
◆品川学園を視察した際、日本の公立学校が平均的な教育に基づいて学生の個々の育成に努力していると感じました。公立学校で学ぶ中日ハーフや中国人の子供たちがこれほど多くいるとは思っていませんでしたが、誰もが非常に鷹揚でゆったりとしていて印象深かったです。訪問先で出会った子どもたちは、大きな声で挨拶をし、中国語で挨拶をする子も多く、皆の好奇心や活力を感じました。埼玉県教育局との交流の中で、日本全国の小中学校で1人1台端末が整備されていることや、ICT技術が広く教育に活用されていることを知りました。しかし同時に、インターネットによって引き起こされる多くの問題もあります。 問題は中国にも共通し、その解決策は多くのアイデアを与えてくれました。言い換えれば、それはクラスの担任に個別に依存するのではなく、そのような問題をすべていじめ対応組織に解決を任せることで、一方では教師独自の対応によって引き起こされる問題を回避し、教師の責任も軽減していて、参考にする価値があります。
◆日本に滞在した数日間、教育者、学生、ソーシャルワーカーを含む日本人の温かさ、礼儀正しさ、活気に感銘を受けました。初日の夜の交流会では、日本人教師の笑顔にとても癒され、品川学園の学生たちの生き生きとした熱意にとても感動し、ホテルのスタッフも私たちに気持ちよく過ごさせてくれました。今回の訪問で感じたのは、日本と中国には青少年の教育面で共通点や特徴があるということです。類似点は、私たち全員が特定の個別の国の状況に基づいて教育に取り組んでいるということです。違いは、重点的に推進している分野とプロジェクトの違いです。埼玉県教育局のインターネットリテラシーに関する報告を聞きましたが、10代の若者を対象とした人工知能リテラシー教育を体系的に設計し、実施していました。千葉大学教育学部附属中学校を訪問した際、将来の才能を育成するために、学生の個別かつ長期的な育成に基づく小中大一体の教育の取り組みを行っていることが分かりました。また、品川学園では、ゴミ分別における日本の特色ある取り組みを実感しました。すべての国が、グローバルな生態文明、教育、持続可能な発展に貢献するために、さまざまな対策を講じていることが分かりました。